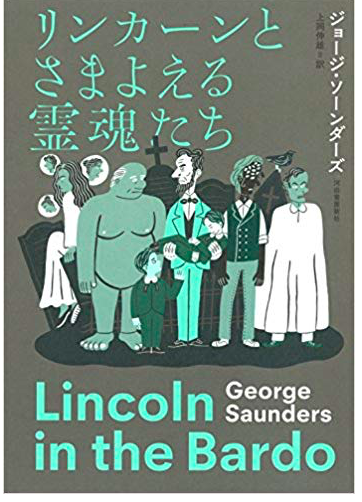2018年7月〜8月に読んだ本
7月〜8月に読んだ本で、記事を書いていなかったものをまとめました。
(案の定)長くなりましたが…。一冊あたりは短いので読んでみてください。
優しい鬼 レアード・ハント
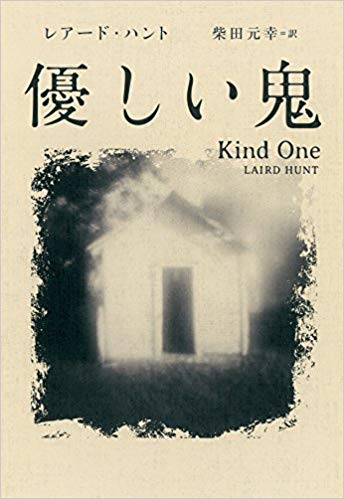
奴隷制があった時代の、中西部(ケンタッキー州シャーロット郡…『パラダイス』)で起きた悲劇。
悲惨な物語は、生々しく開いた傷口を連想させる。ノーベル文学賞作家かつ、黒人女性であるトニ・モリスンの『ビラブド』『青い目がほしい』の痛々しさを思い出させるところがあった。彼女も、黒人たちの苦痛、恨み、憎悪、破壊され尽くした心と体を、克明に、鋭利に描いている。形式自体も少し似ている気がした。寄せてるのか定型があるのか。太古の語り部のようなものを感じさせる。
主な語り手である白人女性・スーは14歳で従兄弟である白人男性に嫁ぐ。スーは、次第に彼らの娘であり奴隷である黒人姉妹に暴行を加えるようになる。だがある日、夫は死に、スーは彼女たちから、粛々と優しく、復讐を始められることになる。根幹に奴隷制の問題があるのだが、スーの視点ではあまり人種に触れられていないので混乱した。巻末の訳者後書きに「自分が奴隷所有者だとわからなくなった白人女性」のエピソードが元とあり、それが意図的に暈されていたことが判る。「鬼」(原作は"One")ってそういう……「優しい鬼」って、あー…って思った。白人女性の罪の塗りつぶしであり、狂気であり、そういうものが「鬼」という表現で為されているのかな。Oneよりも日本語独特の「鬼」表現はいいと思う。「ひと」でもなく「もの」でもなく、「何か」。英語で「鬼」だとまた宗教的な意味合いを帯びてきて、違うものになる気がするから、邦訳ならでは、日本人ならではのニュアンスだと思う。
そういう仕掛けも含め、2度3度読み返さないとなかなか整理できない書き方がされている。改めて見返すと、この本の表紙からしてそうだ、暈されている。それはスーの白濁した意識であり、黒人がもう二度と想起したくない過去であり、消えかける歴史でもある。作中で、黒人奴隷アルフフィブラスが語る『タマネギの話』の重みが良かった。良いというだけでは、違うような気がするのだが、なんと言えばいいのかわからない。凄みがある。口語伝承と黒人、というのはひどく強く繋がっているものだとわかる。それのみが綱のように黒人と黒人の歴史、被虐、血を結んでいる。
アルコフィブラスがいうには、ライナス・ランカスターの道具小屋にあるみたいな鉄を足首につけられてこの国に来たあるコフィブラスのおばあさんはひとの足にクギをつきとおすような話ができたそうだ。(74)
(読書期間:7/18~20)
現代世界の十大小説 池澤夏樹

本好きな方は 池澤夏樹さん編集の『現代世界文学全集』『現代日本文学全集』をご存知だと思う。作家を目指す上で古典や名作を改めて読もうと、自分も何冊か挑戦している。その中で手引きになるかと思い読んだ。一作一作の選考基準、評価はさておき、現代世界文学の潮流、傾向を知る上でよい本と思う。以前記事に書いた『書いて、訳して、語り合う』を併せて読むとなお有意義ではないだろうか。
全体的に今は民話、口語、素朴な物語の状態に立ち返っている感じがあるのだろうか。複雑に凝った物語ではなく、もっと粗野で原始的、しかし根源的である、物語の始まり、発生現場のようなものに関心が高まっているのかも。
アゴタ・クリストフの『悪童物語』の章では、
固有名や時を特定しない民話的な枠組みの中で、救いのない物語を毅然と容赦無く書くことを通じて、象徴性を帯びた寓話に消化させる。(69)
と指摘される。
また、先ほどの『優しい鬼』とも繋がるところなのだが、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』の章では、ガルシア・マルケスが、この作品の語り口を「祖母の話し方」に決めた際の話がひかれている。
…ところがあるとき、「祖母が話を語って聞かせてくれたように語ればいい」とひらめいた。つまり、「身の毛もよだつほど恐ろしいことを、今そこで見て来たように、しれっと話す」のです(「グアバの香り」)。そして完成した「百年の孤独」には、たしかに、文章なのに『民話の語り』がある。(55)
他にも、『悶え神』の話などは非常に惹かれるものがあった。文字を持たなかった人たちがそれでもなお残した強烈な物語、その動機は心に迫る。それは石牟礼道子の『苦海浄土』にまで繋がるものだ。
(読書期間:7/19〜7/20)
マダム・エドワルダ/眼球譚 バタイユ
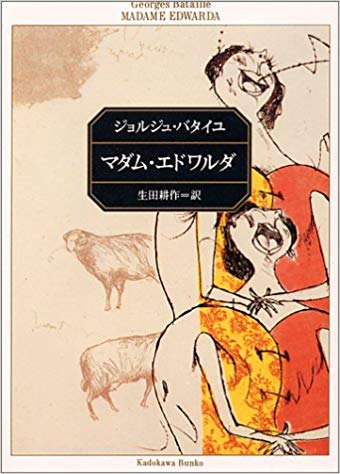
この一冊を読んだんだけど正直『マダム・エドワルダ』はよくわからなかった…。収録順は逆のほうがいいと思う。『眼球譚』ならまだ普通の小説っぽくて分かったから。なんか結構考え方自体は理解できるな、と思ってたら遠い昔に澁澤龍彦を読んだことがあったからだったかもしれない。眼球と卵というイメージの重なりは圧巻かつ白眉。「銀河、大空、太陽、すべてを穢し尽くすこと」でしか興奮を得られないこと、つまりは発狂に至る、世界から明らかに背を背けてしか欲情が得られぬ、そして、その欲情なしでは生きていけないこと。それは世界への不信や鬱憤を背景に、ひどく自己破壊的で、虚無的で、自殺的、自爆的な癖(へき)だといえる。それはある種の悲劇だと思うし、同情もした。最後に収録された討論はとても興味深かったし、羞じ知らずと罵られることも厭わず、堂々とこういう口弁ができたバタイユはやっぱり常人じゃない。ゼロから一人で文学でありエロティシズムである、立派なひとつの哲学である、と昇華出来たのは、やはり爆発的な衝動と文才によるものだろう。
シモーヌはいろんな意味で業が深すぎて、「ええ…」ってなったけど、死に様まで一本貫いててむしろ清々しくさえある。
バタイユに従えば、人間が動物と異なる点は、性と死について不幸な自覚を抱いていることである。快楽(生)も苦痛(死)も等しく禁制の烙印を印されている。 それらは、宗教に類する、神聖な領域を形作る」。苦痛と死に直面して覚える不安感を、快楽と性を前にしても感じるのだ。(262)
こういうふうに、性(や死)の快楽自体を抜きに形骸化した「かたち」だけを、ボソボソはずかしそうに語る人間の姿はバタイユには「去勢された」ものと映り、ごまかしと軽蔑の対象なのだろう。
(読書期間:7/21〜22)
読書の方法―なにをどう読むか 吉本隆明

「読書の方法」はちょうど知りたいところだった。著者については吉本ばななのお父さんということだけは知っていた。読んでみると、軽妙な感じでいい。少女漫画から資本論まで読み漁る、非常に見識の深い方だったとわかった。『何を、どう読むか』という表題だったが、それについては最初の何十ページかで明快に書かれている。つまりは、子供のときのように、一心に読みたいものを、放埓に読む、ということ。それが理想の読書の姿であること。だが、すでに自分はなかなかできないこと。これまでの自分を振り返って、敗戦を経験してがらりと見識が変わった、というくだりからは、古き日本の知識人といった趣がある。女性作家についての話も興味深い(中澤新一、荒俣宏との対談)。たとえば、女性漫画家は煌めくようなものを短期間で書いて、さっと消える、というところなど。
ニーチェの影響を深く受けていたらしい折口信夫を読んでみたくなった。
(読書期間:わすれた)
南方熊楠/柳田國男/折口信夫/宮本常一 (池澤夏樹=個人編集 日本文学全集14)

南方熊楠と折口信夫が読みたくて借りた。 四者四様といったかんじでよかった。 読んで見て、特に南方熊楠と折口信夫は文章になれるのに時間がかかった。。音読したり書き写したりでなんとか消化できた。
熊楠が神社合祀の意見を出してからたった100年しか経ってないと言う事実に驚愕する。心の拠り所を失った田舎の人々の嘆く様が手に取るようだった。どこまでも縦横無尽な知識に溺れそうになる。文章は濃密で、文机に向かい、全身で憤りながら書いている姿が目に浮かぶ。
『死者の書』は本当に素晴らしい。折口信夫の文は絢爛でドロドロ渦巻いてて執念を感じる。平安時代の郎女(お姫様)の生活は本当に、暇だったんだなあと思う。ずっと部屋にこもりきりで、人間としてどうなのかと思う。一方でそれは甘美で…ある意味蕩けるような生活だとも感じる。
屋敷から一歩はおろか、女部屋を膝行り出ることすら、たまさかにもせぬ、郎女のことである。…家に居ては、男を寄せず、耳に男の声も聞かず、男の目を避けて、仄暗い女部屋に起き臥ししている人である。世間のことは、何一つ聞き知りも、見知りもせぬように、おおしたてられてきた。(219)
また、書き出しの「彼の人は〜」の凄み。怪物が闇のなかに、長年の放逐から起き上がり、形なくどろどろと泥のように蠢く感じがよくわかる。半端じゃない。
他収録、柳田国男の文は名前の通り柳のように力まず、さらっと風通しが良い。『妣が国・常世へ』は『木島日記』(大塚英志)で知っていたので、読めてよかった。
初めて読んだ宮本常一の『土佐源氏』は、終盤でうるっと来た。人の心も、男と女も全然変わらないんだな。
(読書期間:7/23〜8/1)
小説禁止令に賛同する いとうせいこう

すばる誌上にて読んだ。面白い。小説の不確実さ、不健全さを指摘し、禁止されて然るべきという体で綴られる、元小説家である「私」の文芸論。執筆者は第三次世界大戦後(?)、分裂した日本で、体制の監視下、収容牢の機関紙への連載というかたちでこの論を書いていく。検閲のために伏せ字にされたと思われる箇所(どうやら東・京、日・本、その他諸々が×になる様子)や、毎回の記事の末尾につく「処罰」報告など、全体にきなくさい臭いがつきまとっている。
「私」の小説禁止令への賛同、つまり小説は危険で不健全で規制されるべきものですよという証明が、逆に小説の面白さ、奥深さを徐々に浮き彫りにしていく。彼がひく作家や小説家は実在する大作家であったり、今も文壇に登場する人物だったりする。そして、その人たちも、彼と同じように収監され監視下に置かれているらしい。どこからが創作でどこからが実在するなのかわからなくなる、そういう騙りが多く使われていて、錯綜する。彼の主張も、彼自身の知識や来歴とは食い違うものである。そもそも、こんなに本が好きで、本に詳しい人間が、小説禁止令に賛同している、わけがないのだ。そうやって様々な箇所に齟齬が産まれてゆく。淡々とした文章の涯てのラストは凄まじい。根本的な読む愉しさに満ちた作品だと思う。
いとうせいこう、ビットワールドのおじさんって思ってたけど実は凄い人なんだな。ひいてくる人物や作品に太刀打ちできなかった。。
(読書期間:8/4〜6)
それから 夏目漱石

「三四郎」の続編的な内容であるといわれる。「三四郎」は何年か前に読んだことがあったので、これを読んでみた。おもしろい。作中に「三四年前」として、三四郎っぽいことが書いてあって、これはそういう意味なのかなと思ったりした。
…その時分は親爺が金(きん)に見えた。相当の教育を受けたものは、みな金に見えた。だから自分の鍍金(めっき)が辛かった。早く金になりたいと焦ってみた。ところが、他のものの地金へ、自分の眼光がじかに打つかる様になって以後は、それが急に馬鹿な尽力の様に思われ出した。(83)
前よりも世間を知って、少し賢くなって、それがゆえに、世界をしなに見るようになった青年の話である。
解説にある「悲劇は狂気に至るまでの自己認識の劇」ということばが深い。 三千代さんが藍色の印象の女性。静かで繊細な女性で、感じやすい質の代助が彼女を好きになるのもわかる気がした。漱石の小説の女性は、レイかアスカのような感じの人が多いと思う。
行き着くところが情熱的で、切烈で、わりと序盤は飄々としていた代助がこうなるのが意外だった。
漱石って固そうなイメージがあるんだけれど、実はすごくお茶目な人だと思う。ちょっとしらばっくれたような、知らんぷりしてて空とぼけてるような、そういう日本語の使い方が気持ちよくて笑ってしまう。小気味がいい。なのに時々豹変して、翻るように美しい言葉を使うからどきっとする。
百合の遣い方、三角関係などがわりとストレートだと読んでわかった。漱石の小説世界をわかりやすく把める作品なんじゃないだろうか。労働とお金について懊悩する代助の姿は全然古く感じない。金に遣われる人間であってはならないが、金がなければ生活は成り立たぬ。代助はこの悩みに一生涯苦しめられていくのだろう。それでも、三千代を取った選択は好かった。一途で心惹かれた。
(読書期間:8/7〜8)
読書について 小林秀雄

小林秀雄は前に硬めの、美学についての本を読んだ。だがこれにはもっとやわらかく、自然なことばで、同じことが書いてあってわかりやすかった。入門にいいかもしれない。『カヤの平』が本当に面白くて、落語のようで普通に笑える。これは柳田邦男の推薦?で教科書にも載ったらしい。小林秀雄自身も『カヤの平』を気に入っていたらしく、選ばれて嬉しいということを書いている。一読の価値有りだと思う。
(読書期間:8/14)
エコー・メイカー リチャード・パワーズ

最近処女作『舞踏会に向かう三人の農夫』が文庫化して話題のパワーズ。これはその彼の全米図書賞受賞作品。交通事故に遭い「カプグラ症候群」という脳障害を患った弟と、その姉カリンの奮闘の話。そうはいっても単なる脳障害の闘病記に終わるはずはなく、ネブラスカ州に毎年降り立つ大量の鶴や9.11以降のアメリカ、自我というものへの根源的な問いかけなど、本書のなかでは種々の要素が入り乱れている。「カプグラ症候群」とは極めて珍しい症例で、それまで患者が親しかったものがすべて偽物に見えるというもの。オリヴァー・サックスを彷彿とさせる、神経科医にして患者の症例を本にして発表してきた小説家(?)・ウェーバーの人物像が興味深い。精神科医に直接受診した人の大抵は抱くであろう不信や落胆も精密に描かれている。利己的な部分も身勝手な部分も。自らが長年身につけてきた欺瞞を剥ぎ取られて、ウェーバーが変質していく様は、何というか憐れでもあるし、原始に戻っていく人間を見る気持ちにもさせられる。
彼の自我、「かつて自分がそういう人間であったところのもの」はどんどん瓦解し、細分化し、彼は医師としても男としてもほとんど生まれ更(か)わったようになる。この「細分化し、還元し、(交わる)」という動きは作中の様々な場所で使われる。
心臓が一拍打つ間にその体はウェーバー本人にとって異質なものになる。そこに住んでいる幽霊たちはバーバラの目には見えない。バーバラはこの身体でしかウェーバーを見たことがないのだ。
やがて身体はさらに異質なものとなる。バーバラからどう見られようと構わない。掛け値無しに本当の自分以外のものに見られたいとは思わない。虚ろでみっともない、権威をはぎとられたもの。誰もと同じで境界線がない。(597)
私個人としては、この「バーバラ」が超人的な存在すぎてあまり共感を抱けなかった。元々カリンの視点から始まった物語なのだが…カリンの清算もあまり済んでいないような感じがある。私が汲み取れなかっただけかもしれないが。ただ伝えたいもののスケールの大きさと構想は評価できると思う。巨きなもの。それがミクロに繋がっていく。それは人と人が結びつこうとする動きとなんら変わらない。私たちは分断され孤絶しているが、連帯し繋がりあうことだけが、成り立ちとして志向されている。たぶん。
(読書期間:8/1〜8/11)
お疲れ様でした。一冊でも気になる本を見つけていただけたら嬉しいです。最後までお読みいただきありがとうございました。